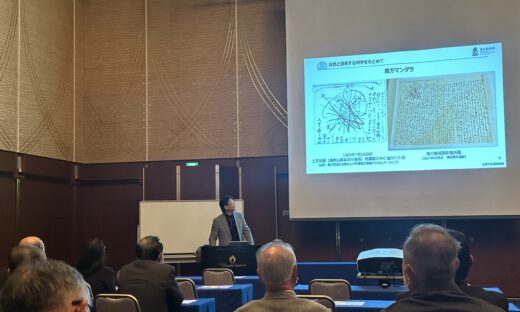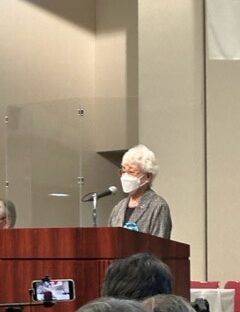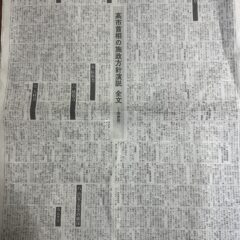和歌山研究会

江戸時代の庶民の教育レベルの高さは驚異的で、布教にきた宣教師たちもびっくり、それを担ったのは「寺子屋」一種の私塾であったのはよく知られています。ヨーロッパの国なんて庶民は読み書きできませんでしたから。
和歌山研究会、今回の講師は荒俣宏先生、「帝都大戦」には私もハマったクチです。寺子屋の様子を描いた浮世絵を示しながら、当時の寺子屋の教育を語ってくれました。
なんとなんと、「寺子屋」では机はテンデバラバラに置かれています。誰も正面なんて向いていません。机の下に隠れるもの、取っ組み合っているもの、面をつけてふざけているもの、もちろん中には勉強してるものもいますが、一見すると学級崩壊?に見えなくもありません。うーんアナーキー。
「寺子屋」では先生に合わせて一斉に論語なんかを素読しているようなイメージがあったのでこれは意外。
明治維新がなり、画一的な国民教育の必要性から黒板に向かって机が並べられるようになったのですね。
それにしても江戸時代の我が国の教育水準は圧倒的な世界一だったのですから、我々は「寺子屋」式教育を学ぶべきかも。めいめいが「寺子屋」での自分の居場所を見つけて、それぞれの課題を学んでいる(どう見ても暴れてるだけのやつもいるけど)いわばオーダーメイドで学んでいたんです。
現代教育の大きな課題である「引きこもり」の解決もここにヒントがるような気もします。
さらに、荒俣先生によれば、素読(繰り返し音読すること)と輪読(グループで文献を読んで発表し合う)が当時の教育の基本らしい。先生は特に教えることをせずに時折質問に答える、基本的には生徒は自主的に学ぶんです。先生の役割は自ら学ぶ生徒たちの手助け。
勉強って机に座って先生の言うことをよく聞いてノートを取って、そんなもんだと思っていましたが、確かにそんなことに向いたやつ以外、教室に居場所がないのはどうなの?落ちこぼれたら、終わりなんて悲しすぎます。「寺子屋」令和に復活してもよいかもね!
ところで我が家には私の居場所はありませんが、どうすれば?そうだスタバへ行こう!トホホ。