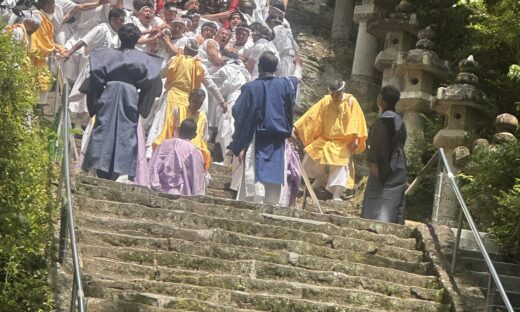参議院選挙がはじまりました

「肘ついてご飯食べるな」「靴脱いだら揃えよ」素直に聞けばいいですが、我が息子は小声で「メンドクサ」などと呟きます。その憎たらしいこと。ほっぺたをひねきって(つねって)やりたいですね。
同じことを私が戦前生まれの父に言おうものなら、「面倒くさいとはなにごとか💢」と父得意の右ストレートが私の頭に炸裂していたことでしょう。
それぐらい嫌〜な言葉である「面倒くさい」
先日行われた党首討論会、石破総理は「この国の将来に責任を持つ」とボードを掲げ、外国人を受け入れる必要性についてふれ、「七面倒くさい日本語、日本の習慣を日本政府の負担によってでも習得してもらい」などと述べて顰蹙(ひんしゅく)をかってます。
ものすごく善意に解釈すれば、外国人から見れば、日本語と日本の習慣は七面倒に感じられるでしょうから、いい人材に来てもらうために日本国政府がお金を出して習得してもらうようにします、ということでしょう。外国人の立場に立ってあげたのね。
でも言葉づかいとしてはなんだかなぁ〜。
やっぱり日本語と日本の習慣がディスられている感じがしますよね。
ロラン・バルトという思想家がいます。めちゃくちゃ難解なのでその著書、「零度のエクリチュール」は私の頭では理解不能ですが、内田樹先生の解説によると、要するに「言葉づかいが人を決める」ということを言いたいらしい。
自分を「俺」というか「僕」というかでは立ち居振る舞いや身なりまで変化する。
就職の面接では髪を短くきって「俺」から「私」に普通は変えますよ。でなきゃ不採用。長髪のミュージシャンには「私」なんて似合いませんし。
「エクリチュール」とは「社会的に規定された言葉の使い方」(内田先生によれば)ある社会的立場にある人はそれに相応しい言葉の使い方をしなければなりません。
石破総理の言葉づかいは総理に相応しいものなのか、どうか、そうじゃなければ、社会(有権者)によりその立場をおわれることになるでしょう。
私も家内のことを「お母さん」と呼ぶようになって久しいですが、今家内を名前で呼んだらどうなる? ちょっと怖い、とても試す勇気はありません。家庭をおわれた大変だ!トホホ。